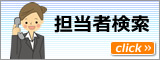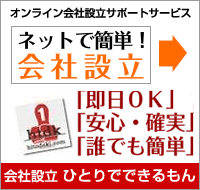最低賃金平均1118円に決定、上げ幅は過去最大 物価高など背景
2025年度の最低賃金(時給)について、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)は4日、全国加重平均で63円(6・0%)引き上げて1118円とする目安を答申した。今春闘の高水準の賃上げや物価高などを背景に、昨年度の50円(5・0%)を上回った。現行方式となった02年度以降、額、引き上げ率ともに過去最大となった。
最低賃金は、企業が労働者に支払う賃金の下限額。審議会は労使と有識者の代表で構成する。賃金の動向や労働者の生計費、企業の支払い能力を考慮し、地域の経済状況に応じて都道府県をA~Cの3ランクに分けて目安を示す。
今年度はAランク(東京、大阪など6都府県)63円、Bランク(北海道、福岡など28道府県)63円、Cランク(岩手、沖縄など13県)64円とした。この目安を踏まえて各都道府県の審議会が上げ幅を決定し、10月ごろから発効する。
目安通りに改定されれば、全都道府県で1000円を超える。最も高い東京都は1163円から1226円、最も低い秋田県は951円から1015円となる。近年は地方の審議会の決定額が目安を大幅に上回るケースもあり、今後の審議が注目される。
7月中旬から始まった今年度の中央審議会の小委員会で、労働者側は長期化する物価高を踏まえ、「最賃に近い時給で働く労働者の生活は昨年以上に苦しくなっている」と主張。昨年を上回る大幅引き上げを求めた。一方、使用者側は引き上げの必要性を認めつつも、中小企業で価格転嫁が十分に進んでいないことなどから「過度の引き上げは経営を圧迫しかねない」と慎重な姿勢を示していた。
厚労省が小委員会に提出した資料によると、総務省の消費者物価指数(持ち家の帰属家賃を除く総合)は昨年10月~今年6月の平均値で前年同期比3・9%増。食料品に限ると同6・4%増となった。
小委員会は最終的に、物価高で家計の負担は増えているとして生計費を重視し、過去最大の引き上げ額で決着した。
最低賃金を巡って、政府は「20年代に全国平均1500円」との目標を掲げている。達成には今年度を含め単純計算で毎年度7・3%の引き上げが必要だが、今年度はこれを下回った。
石破茂首相は「今後も賃上げ5カ年計画を強力に実行し、経営変革の後押しや賃上げ支援のため政策を総動員していく」と語った。【塩田彩、宇多川はるか、大野航太郎】
出典:毎日新聞社
最低賃金の大幅引き上げから考える中小企業経営と『税理士 探し方』の重要性
【はじめに】
2025年度の最低賃金が、全国平均で63円引き上げられ、時給1,118円となる見通しとなりました。これは、2002年度以降で過去最大の引き上げ幅です。地域別では、全都道府県で最低賃金が1,000円を超える見込みで、東京都では1,226円に、最も低かった秋田県でも1,015円となります。
この急激な賃上げは、物価上昇や人件費高騰に悩む中小企業にとって、まさに死活問題といえます。特に価格転嫁が難しい業種や、固定費が高い事業構造を持つ企業にとっては、資金繰りや採算管理を再考する必要があります。本記事では、最低賃金引き上げの影響を踏まえ、税理士としての立場から、経営改善のポイントと、経営を支える税理士の「探し方」について解説します。
【1. 最低賃金引き上げが中小企業に与えるインパクト】
賃金上昇は、従業員にとっては朗報でも、経営者にとっては頭を抱える要因のひとつです。とくに以下のような影響が予想されます:
・人件費の増加により、利益率が圧迫される
・価格転嫁が難しく、売上に直結しにくい業種では特に打撃
・パート・アルバイトの時給調整が必要になり、店舗運営コストが上昇
・結果として、経営戦略の見直しや業務の効率化が求められる
このような局面では、感覚的な経営判断ではなく、正確な数字に基づいた戦略が不可欠です。ここで登場するのが、「信頼できる税理士」の存在です。
【2. 税理士が果たすべき役割】
税理士は、単なる決算・申告の代行者ではありません。人件費の上昇に対して、どのようにコストを吸収するか、補助金や助成金をどう活用するか、利益確保のために事業構造をどう見直すかといった、経営戦略の根幹に関わる支援ができます。
・給与計算や人件費分析による採算の見直し
・中小企業向け補助金・助成金の最新情報提供と申請支援
・設備投資や業務改善による生産性向上のアドバイス
・キャッシュフロー予測と資金繰りの見直し
これらを実現するには、事業内容を深く理解し、経営者の悩みに寄り添える税理士とのパートナーシップが欠かせません。
【3. 「税理士 探し方」5つのステップ】
税理士はどこにでもいると思われがちですが、「誰に頼むか」で結果が大きく変わるのが現実です。最低賃金の引き上げという難局を乗り切るためにも、次のポイントを押さえて税理士を探しましょう。
① 自社業種に強いかを確認:
飲食業、介護業、製造業など、業種によって税制や助成金の制度も異なります。自社と同業の顧問実績がある税理士を優先的に探しましょう。
② 人件費や補助金に詳しいか:
賃金引き上げに関連する助成金(例:業務改善助成金)に強いかどうかも、選定基準のひとつです。
③ 定期的な面談や報告があるか:
数字に基づいた助言を受けるには、月次決算などをきちんと行い、報告してくれる体制が重要です。
④ コミュニケーションが取りやすいか:
質問にすぐ答えてくれる、経営者のレベルに合わせて説明してくれるなど、相性の良さも大事です。
⑤ 料金体系が明確か:
「顧問料+オプション費用」が不明瞭な税理士もいるため、契約前に明細を出してもらいましょう。
【4. 税理士紹介サービスの活用という選択肢】
「税理士 探し方」に悩んでいる経営者の方におすすめなのが、税理士紹介サービスの活用です。例えば、「T-SHIEN」などの税理士マッチングサービスでは、自社の業種・地域・経営規模などの条件に合った税理士を無料で紹介してくれます。
自分で何人も探して面談する時間がない方や、税理士に不満があるが乗り換えのきっかけがない方には、特に有効な手段です。
【5. 最低賃金1500円時代に備える経営戦略】
政府は「全国平均1500円」の最低賃金目標を掲げています。これを達成するには、今後も毎年7%以上の引き上げが続くと予測されます。そうなると、今よりもさらに人件費が企業経営に与える影響は大きくなります。
・労働集約型モデルから脱却する
・クラウド会計や自動化システムで業務を効率化する
・採算が合わないサービスは撤退する
こうした判断をスピーディに行うためにも、税理士と二人三脚で未来の事業設計を行う体制が必要です。
【まとめ】
2025年度の最低賃金引き上げは、中小企業経営に大きな試練をもたらします。しかし、このような変化の時こそ、経営を見直すチャンスでもあります。
数字に強いパートナーである税理士とともに、人件費の見直し、コスト構造の再設計、助成金の活用などに取り組むことで、企業の未来はより明るいものとなるでしょう。最初の一歩は、「自社に合った税理士の探し方」を知ることです。
「税理士 探し方」で迷ったら、まずは専門サービスに相談してみてください。経営に寄り添う、心強い味方が見つかるはずです。
2025年08月05日

最適な税理士が見つかる!
T-SHIEN税理士マッチング
依頼したい税理士業務と希望金額を入力し、匿名で全国の税理士事務所から見積を集めることができるシステムです。送られてきた見積の中から、最適な税理士を選ぶことができます。